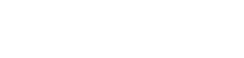路線価と固定資産税評価額とは?実勢価格との違いと相続・購入での活用ポイント
不動産の評価額にはさまざまな種類があり、初めて不動産の相続や購入を検討する方は「路線価」や「固定資産税評価額」といった言葉に戸惑うかもしれません。実は、一つの不動産には「一物五価」(いちぶつごか)と呼ばれるように、複数の価格が存在しますつまり実勢価格(市場の取引価格)と、公的に定められた公示地価・基準地価・相続税路線価・固定資産税評価額の5つの指標があるのです。それぞれ算出主体や目的が異なり、評価額も違います。本記事では特に主要な指標である「路線価」と「固定資産税評価額」を中心に、これらが何を意味するのか、実勢価格とどう違うのか、そして不動産の売買や相続でどのように活用できるかを詳しく解説します。公的指標を正しく理解し、上手に活用することで、不動産に関する判断や戦略に役立てましょう。
不動産に複数の評価額が存在する理由(「一物五価」とは)
不動産には前述の通り5種類の価格指標が存在し、これを指して「一物五価」と言います。以下がその概要です。
実勢価格(市場価格)
実際に市場で売買が成立する価格です。売り手と買い手の需給関係で決まるため、定価は存在しません。景気や需要により変動し、人気エリアでは公的評価より高く取引されることもあれば、人口減少地域では公的評価より低い価格で取引されることもあります。一般に、公示地価に対して実勢価格は平均110%程度(1.1倍)になるとも言われますが、地域や個別事情で大きく異なります。
公示地価(公示価格)
国土交通省が毎年3月に公表する、その年1月1日時点の標準地の価格です。土地取引の指標として利用され、公共事業用地の補償額算定などにも使われます。一般に実勢価格の70~90%程度の水準と言われ、都市部では実勢に近く、地方では実勢を下回る傾向があります。
相続税路線価(路線価)
国税庁が毎年1月1日時点の価格を算出し、7月に公表する土地の評価額です。主に相続税や贈与税の課税評価基準として利用されます。道路(路線)ごとに標準的な宅地の1㎡あたり価額が定められており、その道路に面する土地は基本的にその路線価をもとに評価されます。後述するように、公示地価の約80%程度の水準で設定されるのが一般的です。
固定資産税評価額
市町村が不動産(土地・家屋)の価格を評価し、固定資産税や都市計画税などの課税標準とするものです。評価は法律に基づき3年ごとに見直され(評価替え)、価格水準は公示地価の約70%程度になるよう調整されています。土地だけでなく建物にも評価額が設定され、建物は経年による価値減少(減価償却)が評価額に反映されます。
以上のように、不動産には複数の評価額があります。それぞれ目的や算出方法が異なるため、用途に応じて使い分けることが大切です。次章以降では特に④路線価と⑤固定資産税評価額に焦点を当て、それぞれの特徴や役割、実勢価格との関係について詳しく見ていきましょう。
路線価とは:相続税評価の基準となる土地価格
路線価の定義と算定方法
路線価(相続税路線価)とは、国税庁が毎年公表する土地評価額の指標で、相続税や贈与税の計算基準として用いられます。具体的には、土地の価額が概ね同じと認められる一連の宅地が面するそれぞれの道路(路線)ごとに、「1㎡あたりの価格」が設定されています。評価時点は毎年1月1日で、その年の地価動向を踏まえた価格が算出され、例年7月頃に国税庁から公表されます。路線価は千円単位で表示され、国税庁のウェブサイト上で地域ごとの「路線価図」として閲覧できます。
路線価地域(主に市街地)の土地について相続税評価額を計算する際は、その土地が面する道路の路線価を基準にします。例えば、ある道路の路線価が「200千円/㎡」と示されていれば、その道路に面する標準的な宅地の評価単価は1㎡あたり20万円という意味です。実際の評価額は、土地の形状や奥行きなどに応じて補正率(奥行価格補正、側方・二方路線影響補正等)を掛けたうえで面積を乗じて算出します。一方、路線価が定められていない地域(郊外や山林等)では評価倍率表による「倍率方式」で評価します。倍率方式では、市町村が評価した固定資産税評価額に一定の倍率(地域ごとに国税庁が定める数値)を掛けて相続税評価額を算出します。つまり、日本全国どこでも相続税評価額を計算するための基準が用意されているわけです。
相続税・贈与税における路線価の役割
路線価は、相続や贈与で不動産を取得した際に課される相続税・贈与税の土地評価基準として、非常に重要な役割を果たします。相続税の申告時には、被相続人から受け継いだ土地を路線価または倍率方式で評価し、その評価額にもとづいて税額を算出します。路線価による評価額は多くの場合、実際の市場価格より低めに設定されるため(後述の通り公示地価の約80%水準)、結果的に課税評価額が圧縮される効果があります。これは不動産にかかる相続税の負担を一定程度軽減する目的もあり、現金や有価証券に比べて土地の相続税評価額が低く抑えられる要因となっています。実際、「土地は現金よりも相続税評価額が下がりやすいので、相続税も安くなりやすい」と指摘する専門家もいます。そのため、不動産を活用した相続税対策(例:現金を不動産に換えて評価額を下げる)も行われるほどです。
贈与税の場合も同様に、例えば親から子へ土地を贈与する際はその土地の評価額として路線価等にもとづく相続税評価額を使用します。土地の評価額が実勢価格より低いため、現金を直接贈与するよりも同じ価値の不動産を贈与したほうが課税上有利になるケースもあります。ただし、不動産を低い評価額で親族に売却・贈与し過ぎると、税務上「時価より著しく低い譲渡は差額分が贈与とみなされる」リスクがある点に注意が必要です。
路線価と実勢価格の乖離
路線価は前述の通り公示地価の約8割、水準によっては実勢価格の7割程度になるケースも多く、市場価格とは乖離があります。路線価 ≒ 公示価格×80%という基準は、バブル崩壊後の1992年以降に「課税評価額を時価に近づける」との方針で採用された経緯があります。それでも市場の実勢とは差がありますし、路線価発表までタイムラグがあるため、急激な地価変動期には乖離が大きくなることもあります。
一般には「路線価は実勢価格より低い」のが普通で、「路線価で評価された土地は実際には路線価以上で売れる」と考えがちです。しかし、必ずしも実勢価格が路線価を上回るとは限りません。土地の需給が弱く市場が低迷している場合や、個別の土地にネック(接道条件が悪い、形が悪い等)がある場合、売却価格が路線価を下回ってしまうケースも実際にあります。東京国税局の解説でも「一般的に路線価は公示価格の80%程度だから路線価より高く売れると想像しがちだが、実際には路線価より低い価額でしか売れないケースがある」と注意喚起されています。つまり、路線価は市場価値を正確に保証するものではなく、あくまで税法上の評価基準である点を押さえておきましょう。
なお、路線価図を読み解くことで、その地域の地価水準や土地ごとの評価額を知ることができます。相続税の試算をする際は、国税庁ホームページの「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」で該当エリアの路線価を調べ、自分の土地の面積を掛け算すればおおよその評価額が算出できます(形状による補正や特例がある場合は専門家への確認が必要です)。路線価図上にはアルファベットや数字が記載されており、それぞれ評価倍率表や地域ごとの補正率に対応していますが、これらはかなり専門的なため、不明点があれば税理士など専門家に相談すると良いでしょう。
固定資産税評価額とは:不動産税の基準となる公的評価
固定資産税評価額の仕組みと算定方法
固定資産税評価額とは、市区町村が固定資産(土地・家屋)の価値を評価した金額で、固定資産税や都市計画税などの課税ベースになります。地方税法に基づき3年ごとに評価替え(見直し)が行われるのが大きな特徴です。原則として一度評価額が定められると、その評価替え期間(3年間)は地価が多少変動しても評価額は据え置かれます。ただし、地価が大きく下落した場合には据え置きによって評価額が実勢と乖離し過ぎないよう調整措置が取られることもあります。
土地の固定資産税評価額は、各自治体の固定資産評価基準にもとづき、公示地価などの時価の7割程度を目途として評価されています。これは税負担を過重にしない配慮から定められており、実際に「固定資産税評価額は公示地価の約70%水準に調整されている」と解説されています。例えば公示地価1㎡あたり10万円の土地であれば、固定資産税評価額は7万円前後に抑えられるイメージです。評価手法として、市街地の土地は路線価に類似した「固定資産税路線価」が道路ごとに設定されており、それを基準に画地補正等を行って評価額を算出します。一方、市街地以外の土地では周辺の標準宅地の価格から算出する「標準宅地比準方式」が採用されています。
建物(家屋)の固定資産税評価額は、新築時の建築費相当額から経年減価補正を行い算出します。木造家屋であれば経年により評価額が減少していき、最終的には資産価値0に近づくような評価カーブが設定されています。鉄筋コンクリート造等の耐用年数が長い建物は減価のスピードも緩やかです。新築住宅には一定期間、固定資産税の減額特例(例:新築戸建て住宅は120㎡までの部分について固定資産税が3年間半額など)もありますが、これらも固定資産税評価額にもとづいて計算されます。
評価替えのタイミングと税負担への影響
固定資産税評価額は3年ごと(※原則)に見直されます。例えば直近では2021年度に評価替えが行われ、次回は2024年度がそのタイミングに当たります。評価替えでは基準日時点の地価水準に合わせて各地の路線価や標準宅地価格が見直されます。その結果、地価が上昇傾向の地域では評価額が上がり、下落傾向の地域では評価額が据え置きないし下がることになります。実際、愛知県の発表によれば2024年度評価替えで県内54市町村のうち30市町村で基準宅地価格が上昇、21市町村で下落、3市町村で据え置きという状況でした。つまりエリアによって明暗が分かれており、地価動向が固定資産税評価額に反映される結果となっています。
評価額が上がればその分、税負担も増えます。固定資産税は課税標準額(通常は固定資産税評価額と同額)に税率1.4%(標準税率)を乗じて算出されます(都市計画税は別途最大0.3%)。税率自体は全国ほぼ一律ですが、評価額が上昇すると税額も直結して上がります。例えば評価額が1,000万円から1,100万円に上がれば、固定資産税は14万円から15.4万円に増える計算です。また、都市計画税(市街化区域内の土地・家屋に課税)も評価額に対して0.3%程度課税されるため、合わせた負担増になります。
固定資産税評価額の動向は、不動産オーナーの長期的なコストに影響します。地価上昇局面では資産価値は上がりますが、その一方で毎年の税コストも増加する点に留意が必要です。逆に地価下落局面では評価額が据え置かれるケースが多く、実勢価格より評価額が割高になることもあります。このように市場とのズレが生じた場合には、納税者は評価替えを待たずに固定資産税評価額の是正を求めることも可能です。各市町村の固定資産課税台帳は毎年4~5月に縦覧(一般閲覧)が認められており、自分の土地の評価額を確認できます。もし「市場価格に比べて評価額が高すぎるのでは?」と思う場合は、市町村の担当部署に相談したり、固定資産評価審査委員会に不服申立てを行うことも検討できます。
地方財政と固定資産税評価額の関係
固定資産税は各自治体(市町村)にとって重要な歳入です。地方公共団体全体では税収の中で固定資産税が占める割合は大きく、2022年度決算ベースで市町村税収の約41.4%を占める基幹税となっています。したがって、固定資産税評価額の適正な維持は自治体の財政運営に直結します。評価額を3年据え置きとしつつも、市場変動に応じて見直す制度は、税収の安定と公平な負担の両立を図る仕組みと言えます。
また、固定資産税評価額は固定資産税以外にもさまざまな場面で使われます。例えば都市計画税(市町村税)の課税標準、不動産取得税や登録免許税(いずれも都道府県税・国税)の算定基準にもこの評価額が用いられます。つまり、不動産を所有・取得する際の公的コストの多くが固定資産税評価額に基づいて決まっています。このように税や行政の基礎となる評価額であるため、公平性確保の観点からも評価替え時には学識者や不動産鑑定士を含む「固定資産評価審議会」で専門的な審査が行われています。自治体により公表度は異なりますが、愛知県では評価替えごとに各市町村の基準宅地価格や路線価の変動状況をプレスリリースとして発表しており、納税者にも情報提供されています。
公示価格・実勢価格との違いを理解する
路線価と固定資産税評価額を理解するには、基準となる公示価格(地価公示)や市場の実勢価格との関係性も押さえておく必要があります。すでに述べたように、公示価格は国が発表する標準地の時価に近い指標で、路線価・固定資産税評価額はそれぞれ公示価格の一定割合を目途に設定されています。一般的な水準をまとめると以下のようになります。
公示価格
実勢価格のおよそ90~100%程度(平均すると実勢価格の約90%〜とされます)。ただし需給により実勢より低い場合も高い場合もあります。
相続税路線価
公示価格の約80%程度。したがって実勢価格の6~8割程度になることが多いです。
固定資産税評価額
公示価格の約70%程度。実勢価格の5~7割程度の水準が一般的です。
例えば実勢価格が1億円前後と見込まれる土地でも、公示価格ベースでは8,000~9,000万円、路線価評価では6,400~7,200万円、固定資産税評価額では5,600~7,000万円といった具合に低く評価されるわけです(地域により差異あり)。このように、市場価格→公示価格→路線価→固定資産税評価額の順に水準が低くなっていくのが一般的な構図です。公示価格と基準地価はほぼ同水準ですので、ここでは公示価格に一本化して説明しています。
公示価格や基準地価は「適正な時価」として発表されるものの、実際の取引価格(実勢)はそれより高いことも低いこともあります。不動産取引では個別性や交渉力、タイミングなど様々な要因で価格が決まるため、公示価格等と完全に一致するケースの方が少ないでしょう。一方で路線価や固定資産税評価額は、税負担に直結することから市場より低めに抑えられる仕組みになっています。言い換えれば、不動産を所有していると市場価値より低い評価で課税される(=評価分だけ税金が安く済む)という側面があります。そのメリットを享受できる反面、先述のように市場が低迷した場合は評価額とのギャップが不利に働くこともありますので、動向を定期的にチェックすることが重要です。
不動産購入・売却・相続・投資で評価額をどう活用するか
公示価格・路線価・固定資産税評価額と実勢価格の違いを踏まえると、これらの評価額は不動産の取引や相続、投資判断においてさまざまな場面で参考になります。ここでは具体的な活用ポイントをケース別にまとめます。
不動産を購入するとき
物件購入検討時には、まず市町村から公表されているその物件の固定資産税評価額を確認してみましょう。固定資産税の課税明細書などに記載された評価額を見れば、年間の固定資産税負担額(評価額×1.4%)がおおよそ把握できます。また、評価額から逆算しておおよその市場価格を推測することも可能です。一般に「固定資産税評価額 ÷ 0.7」で公示価格水準が計算でき、さらにそれを1.1倍程度すると実勢価格の目安になるとされています。例えば評価額5,000万円の土地であれば、公示価格約7,142万円、想定実勢価格約7,856万円前後といった具合です。売出価格とこれら推定値を比較すれば、極端に割高・割安でないか判断する材料になります。ただし個別物件の事情(接道条件や形状、周辺相場)によって適正価格は変動しますので、あくまで参考情報として活用し、最終的には不動産会社の査定や周辺の成約事例も踏まえて判断してください。また、路線価図を見ればその土地の相続税評価額も算出できます。将来的に相続した場合の評価額を知っておけば、「もし今後この土地を子どもに残したらどれくらいの相続税評価になるか」といった予測も可能です。
不動産を売却するとき
売却を検討する際も、公示価格や路線価、固定資産税評価額は価格戦略の参考になります。例えば路線価は毎年発表されますが、路線価が上昇しているエリアでは売却価格が想定以上に伸びる可能性があります。路線価の上昇=地価上昇トレンドのひとつの指標ですから、「路線価が上がった今が売り時」と判断することも理にかなっています。一方で路線価上昇は相続税や固定資産税の負担増も意味しますから、今後長く所有を続けるほど税コストが増えると見込まれる場合、早めに売却して身軽になるという選択肢も考えられます。逆に路線価が下落傾向の地域では無理に売り急がず、次の地価上昇局面を待つ戦略もあるでしょう。また、固定資産税評価額は売却時に買主へのアピール材料になることもあります。「この物件の固定資産税評価額は◯◯万円です」と提示すれば、買主は購入後の固定資産税負担を具体的にイメージできますし、評価額と販売価格を比較して割安感・割高感を判断する材料にもなります。買主から見ても、評価額と売出価格を比較するのは合理的な手法です。例えば「売出価格が固定資産税評価額の2倍近いが、このエリアの相場では通常1.5倍程度だから少し高めだ」といった分析も可能です。こうした情報は価格交渉にも使えるでしょう。ただし前述のように、需給次第では路線価より低い価格でしか売れない場合もあります。特に不動産市況が悪化しているときや条件が悪い土地では、公的評価額が買い手の心理的な下限価格になってしまうケースもある点に注意が必要です。
相続で不動産を評価するとき
相続発生時には、被相続人が残した不動産を相続税評価額で評価し直す作業が必要になります。その際、路線価図や評価倍率表を使えば土地の評価額を自分でも計算可能です。早めに調べておけば、相続税のおおまかな額を事前に試算できるでしょう。評価額は相続人間の遺産分割協議でも客観的な指標になります。例えば兄弟で不動産と預金を分け合う場合、「土地は固定資産税評価額◯◯万円なので、それを基準に配分しよう」という具合に公的評価額を根拠として提示すれば、話し合いがスムーズになることがあります。もっとも固定資産税評価額や路線価は実勢価格より低いのが一般的なので、不動産を取得する側が有利になりすぎないよう配慮は必要です。必要に応じて不動産会社の査定額(実勢ベース)や不動産鑑定士の評価額も参考にし、公的評価額と実勢価格の乖離が大きい場合には調整することも検討しましょう。また、相続対策として生前に不動産を購入しておくと評価額を抑えられることは前述の通りですが、不動産自体に流動性リスク(すぐ売れないリスク)や維持コストが伴う点にも留意が必要です。相続税だけに目を向けず、トータルの資産戦略として専門家と十分に検討しましょう。
不動産投資を検討するとき
投資家にとって公示価格や路線価、固定資産税評価額はリスク管理と戦略策定の材料になります。まず固定資産税評価額を把握すれば、その物件の保有コスト(固定資産税・都市計画税)が算出できます。年間家賃収入に対する税負担率を計算し、収益シミュレーションに組み込むことは必須です。評価額に対して異常に高い価格で購入してしまうと、将来売却時に評価額との差が大きく、買い手が付きにくかったり担保評価が出にくかったりするリスクもあります。一方で「固定資産税評価額に対して割安な物件」は投資妙味があるようにも思えますが、何らか市場から敬遠される理由(借地権付き、再建築不可等)が潜んでいないか注意が必要です。公示価格や路線価の推移も確認しましょう。路線価が毎年上昇しているエリアであれば中長期的な値上がり益(キャピタルゲイン)が期待できますし、反対に下落が続くエリアは賃料下落や空室リスクにも注意が必要です。さらに、将来的に相続を見据えるなら路線価ベースで資産評価をシミュレーションしておくことも有用です。評価額に対して多額の借入金がある場合、その差額が相続税の課税対象になります。不動産投資は実勢価格と公的評価額のギャップが利益にも損失にも作用しうるため、双方を把握して慎重に判断することが重要です。
評価額と実勢価格のギャップを戦略に活かすポイント
最後に、路線価・固定資産税評価額と実勢価格の差異を踏まえた戦略的判断のポイントをまとめます。
不動産は現金よりも低い評価額で課税されるメリット
繰り返しになりますが、土地の相続税評価額(路線価評価)は時価より20~30%ほど低く算定されるのが一般的です。同じ1億円相当の資産でも、現金で持っているより土地として持っていた方が相続税評価額は圧縮され、結果的に納める税金も少なくて済む傾向があります。このメリットを活かし、現金を不動産に換えて生前贈与する、あるいは相続まで保有し続けるといった節税策が取られることがあります。ただし、不動産そのものの管理・維持にはコストがかかる点や、市場価値が下落するリスクもある点には注意しましょう。評価額が低いからといって実際の経済価値まで損なわれないわけではありません。
路線価上昇局面での意思決定
地価が上がり路線価が連動して上昇しているときは、不動産売却の好機である可能性が高まります。路線価は前年から何%上がったか公表されますので、それがプラスで大きければ、近隣の取引事例も値上がりしている蓋然性が高いと考えられます。特に路線価が大幅上昇した年は、固定資産税評価額の次回改定での上昇も見込まれます。売却するなら負担増前の今、保有を続けるなら将来の税負担増を織り込んでおくなど、路線価動向を踏まえて計画を立てると良いでしょう。一方で、路線価が下落している局面では慌てて売却せず、低い評価額の間に相続対策を進める(例えば二次相続を見据えた資産分割を行っておく)といった判断もあり得ます。
不自然な安値取引はNG
親族間や知人間で不動産を売買・贈与する際に、「評価額が低いから」と極端な安値で譲渡すると、税務署から贈与とみなされ追加課税されるリスクがあります。税法上、時価とかけ離れた価格で資産移転を行うことは課税逃れと見做されるためです。公示地価・路線価・固定資産税評価額はいずれも公的な指標ですが、市場実勢とかけ離れた金額で売買すると贈与税が発生し得ることは覚えておきましょう。適正な範囲での譲渡であれば問題ありませんが、「市場価格の半分以下で親に不動産を買ってもらう」ようなスキームは危険です。
評価額乖離への対処法
前述の通り、市場価格と公的評価額が逆転する状況も起こり得ます(市場が低迷し実勢価格が路線価を下回る等)。こうした場合、そのままだと相続税評価額の方が高く算定され、過大な相続税を払う羽目になることも考えられます。根本的には評価基準が法律で決まっている以上避けられませんが、例えば相続発生前に早めに売却して現金化しておく、あるいは不動産鑑定士に鑑定評価を依頼して適正な時価を把握し納税資金を準備しておくなどの対策が考えられます。また、固定資産税については前述のように評価額が不当に高ければ審査請求で是正を求めることもできます。不動産市況の長期的なトレンドも踏まえ、公的評価額と実勢価格のギャップを常に意識しておくことが重要です。
複数指標を組み合わせて判断
最後に、どの指標もそれ単独では不完全である点を強調しておきます。路線価だけで土地の価値を語ることも、固定資産税評価額だけで売買判断をすることも適切ではありません。公示価格・路線価・固定資産税評価額にはそれぞれ目的があり、市場とは異なる前提で作成されています。それぞれを比較・補完しながら総合的に判断することが肝要です。例えば実勢価格を知りたいなら公示価格や周辺の成約事例を調べ、課税額を知りたいなら固定資産税評価額を確認し、相続税を計算したいなら路線価を調べる、といったように目的に応じて使い分けましょう。公的評価額と実勢価格の両面を見るクセを付けておけば、不動産取引や資産承継において大きなミスを避け、より賢明な判断ができるはずです。